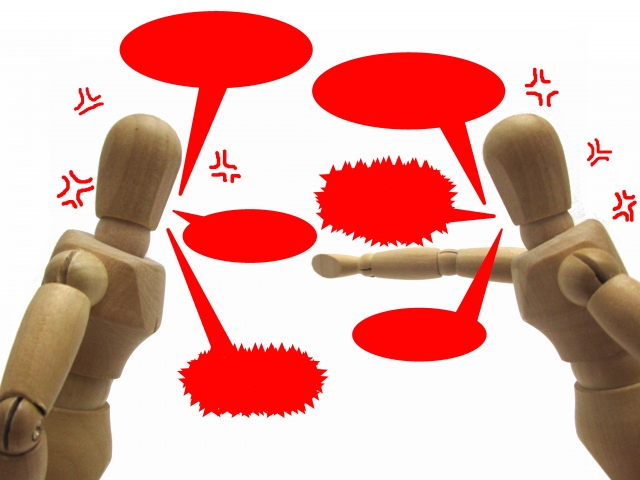相手の誤りを指摘しない 616
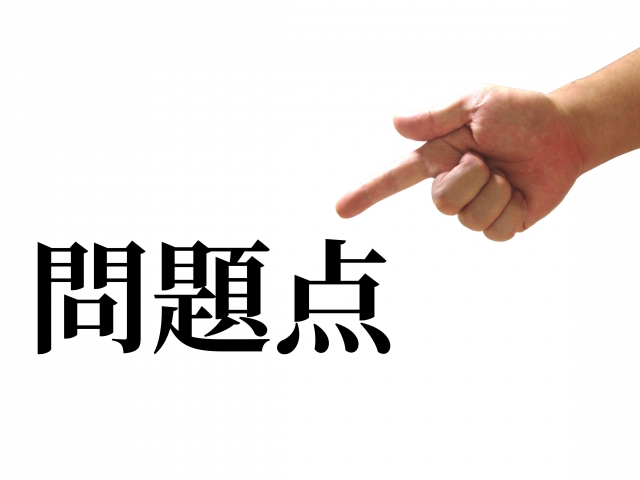
頭がいい人で、するどく相手の話の誤りを指摘する人がいます。
感心するほど、鋭く問題点等を指摘します。
○「その考えは、おかしいと思います」
○「言っていることに、一貫性がありません」
○「話していることには、問題点が多いです」
このような言葉で指摘します。
言われた相手の人は、そう言われると、話ができなくなります。
自分の言っていることが、誤りであると指摘されて、怒りが込み上げます。
はたして相手の話を指摘することが、いいことなのでしょうか。
アメリカの建国時代に政治家として、科学者として、さらに「成功哲学」を説いた賢人として知られるのが、ベンジャミン・フランクリンです。
フランクリンは移民の子で、貧しい少年時代を過ごしましたが、やがて成功者の仲間入りを果たしました。
「君、そこは違うよ」「それは正しくないよ」というように、厳しく相手の誤りをついていくのがフランクリンの論争の仕方でした。
ところがある時、自分が正しいと信じて徹底的にやり込めても、決して相手は仲良くしてくれないことに気づきました。
論争に勝ったところで、相手は自分の言う通りに動いてくれないことがわかったのです。
仮にフランクリンの方が正しい時でも、「君は間違っている」と言われて、「はい、そうですか。改めます」と言う人は一人もいなかったのです。
ほとんどの人は、「自分が正しい」と思って生きているからです。
誤りを指摘しても、決して人々を味方にすることはできないとわかった時から、フランクリンはやり方を変えました。
彼は、「自分は正しい。君は間違っている」と正面から相手をたたくことをやめて、相手の立場を尊重するようにしたのです。
「なるほど。そういう考えもありますね。私はこう考えますが、いかがでしょう」「いいアイデアですね。でも私はこう思いました」というようにイエス・バッド型の会話をしたのです。
相手を立てたり、ほめたりした上で、自分の主張を述べるようにしたのです。
すると、敵の多かったフランクリンに協力者が、たくさんできるようになってきたのです。
やがて、政治の世界でフランクリンは成功します。
それもこの譲歩して相手を尊重することの実践が、大きく役立ってくれたのです。
フランクリンがイエス・バット型の会話に変わったように、私たちも相手の話を聞いた時は、たとえ誤りでも指摘するのでなく、相手の立場を十分理解し、相手を立て、ほめたりした上で、自分の考えを述べるようにしたいものです。
相手の誤りを指摘することは、自分が相手に勝ちたいという思い上がりなのです。
常に相手の立場や思いを十分理解し、人間味のある温かい言葉で、自分の話をするようにしましょう。